政府がセキュリティ・クリアランス制度の運用基準案を公表
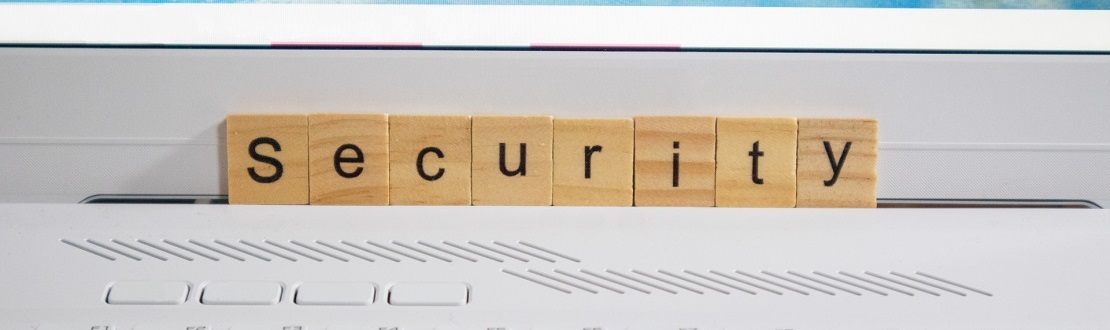
2024年11月26日、政府は経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度に関する運用基準案を公表しました。この制度は、「重要経済安保情報」に指定された情報にアクセスする必要がある者を政府が調査し、情報を漏らすおそれがないという信頼性を確認した上でアクセスを認める制度です。重要経済安保情報の取り扱いは情報管理ルールに従って行い、漏えい時には罰則が科されます。
また、政府は11月28日からこの運用基準案に関するパブリックコメントの募集を開始しました。受付締切日時は12月27日となっています。
制度創設の背景と経緯
経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度の枠組みは、2024年5月に成立した「重要経済安保情報の保護および活用に関する法律」により創設されました。この法律は、経済安全保障を強化するために、特に重要な情報を取り扱う際の信頼性の確認を義務づけています。
この法律の施行は2025年5月を予定しているため、それに先立ち、今回の運用基準案が公表されたことになります。
セキュリティ・クリアランスとは
セキュリティ・クリアランス制度とは、安全保障上重要な情報として指定した情報(以下、CI (Classified Information)と表記)にアクセスする必要がある者を政府が調査し、情報を漏らすおそれがないという信頼性を確認した上でアクセスを認める制度です。ただし、実際にアクセスするには、当該情報を知る必要性(いわゆるNeed to Know)が認められることが前提となります。CIの取り扱いは情報管理ルールに従って行い、漏えい時には罰則が科されます。
日本には、既にセキュリティ・クリアランスを含むCI保全制度として、特定秘密保護法に基づく特定秘密制度が存在しますが、この制度では、経済安全保障に関する情報が明示的に保全の対象になっているわけではありませんでした。しかし、安全保障の概念は防衛や外交だけでなく、経済・技術の分野にも拡大しており、経済安全保障分野においてもセキュリティ・クリアランス制度の整備を通じて、我が国の先端技術情報の保全を強化する必要があります。さらに、セキュリティ・クリアランス制度の導入により、経済・技術分野でも国家間での機密情報の共有が可能となり、民間事業者においては次世代技術の国際共同開発や新産業領域への参画が促進され、ビジネスチャンスの拡大や競争力の向上に繋がると期待されています。
しかし、制度の導入には、いくつかの懸念があります。例えば、広く国民の議論を必要とする情報を政府が秘密指定することで、国民の「知る権利」が侵害される可能性が指摘されています。さらに、これを明らかにした報道関係者や市民が制度のもとに厳罰に処されることも懸念されます。また、制度の運用に伴い、民間人が調査対象になることでプライバシーが侵害されるリスクもあります。こうした懸念にも留意した上で、今回、制度の運用基準案が提示されたことになります。
運用基準案の概要
今回公表された運用基準案は、重要経済安保情報の指定、指定の有効期間、適性評価の実施、適合事業者の認定などについて、統一的な運用を図るための詳細な要項を設けています。
重要経済安保情報の指定
重要経済安保情報として指定される情報は、①重要経済基盤保護情報該当性、②非公知性、③秘匿の必要性の3要件に該当するものとされます(特別防衛秘密及び特定秘密に該当するものは除く)。具体例として、重要なインフラ事業者に対してサイバー攻撃等が行われた場合を想定した、政府としての対応案の詳細に関する情報や、重要物資のサプライチェーンの脆弱性に関する情報などがこれに該当します。ただ、指定にあたって遵守すべき事項として、3要件の該当性を厳格に判断し、必要最小限の情報を必要最低限の期間に限って指定することを必要とします。また、法令違反の事実等を隠蔽を目的として指定しないこと、国民に対する説明責任を怠ることのないよう、指定する情報の範囲が明確になるように努めることなどを遵守するとしています。
指定の有効期間
指定には有効期間が設定され、満了する前に指定の理由の点検や延長の有無が判断されます。さらに、年1回以上定期的に、指定の理由を点検させ、前述の3要件を満たしていないと認められた場合は速やかに指定が解除されます。指定が解除され又は有効期間が満了した場合は、歴史公文書等として国立公文書館等へ移管、あるいは内閣総理大臣の同意を得て廃棄されるとしています。
適正評価の実施
適正評価の実施に当たっての基本的考え方として、①基本的な人権の尊重、②プライバシーの保護、③法に定める7つの調査事項以外の調査の禁止、④適正評価の結果の目的外利用の禁止の4つが示されています。特に②に関して、適合事業者の従業員が適正評価の対象となる場合は、行政機関の職員と異なる立場であること等を考慮し、分かりやすい説明を実施し理解を得ることが必要となります。さらに、質問票に記入した個人情報は、行政機関において適正評価に関わる職員のみが取扱い、本人の上司その他の者が知るところのないようにするとしています。なお、③における7つの調査事項とは下記を指します。
- 重要経済基盤(重要なインフラや重要物資のサプライチェーン等)毀損活動との関係に関する事項
- 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
- 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
- 薬物の濫用及び影響に関する事項
- 精神疾患に関する事項
- 飲酒についての節度に関する事項
- 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
なお、適正評価は、本人の同意を前提に、内閣総理大臣による一元的調査の結果に基づき、各行政機関の長が実施するとしています。
適合事業者の認定
行政機関が重要経済安保情報を提供する必要がある事業者を選定し、事業者からの認定申請に基づき、情報を適切に保護できると認められる事業者を適合事業者として認定するとしています。認定後は、適合事業者と重要経済安保情報を提供するための契約を締結し、さらにその後、情報の取扱いが見込まれる従業員に対して、適正評価が実施されます。
より詳しい内容については、内閣府のウェブサイトをご確認ください。
まとめ
セキュリティ・クリアランス制度は、重要経済安保情報を守るための新しい枠組みであり、その運用により、我が国の誇る先端技術流出のリスク等を大幅に低減することが期待されています。また、安全保障の強化だけに留まらず、民間事業者が国際共同研究等に参加できるようになること等、ビジネスチャンスが広がることも期待されます。しかし、その実施には国民の知る権利やプライバシーを侵害しないよう考慮する必要があります。しかし、この制度が、強固な経済安全保障を実現するための重要なステップであることは間違いありません。
また、現在セキュリティクリアランス制度は “誰に” 機密情報を開示するか、という問題に焦点が当たっていますが、その次のステップとして、その人に “どのような方法で” 情報を開示するかという問題が出てくると予想されます。
弊社はIRM(Information Rights Manegement)システムを開発する暗号化ソリューションのメーカーとして、今後、データに対してどのように制御を行うかという議論が深まっていくことを期待します。
カタログ・資料ダウンロードはこちら
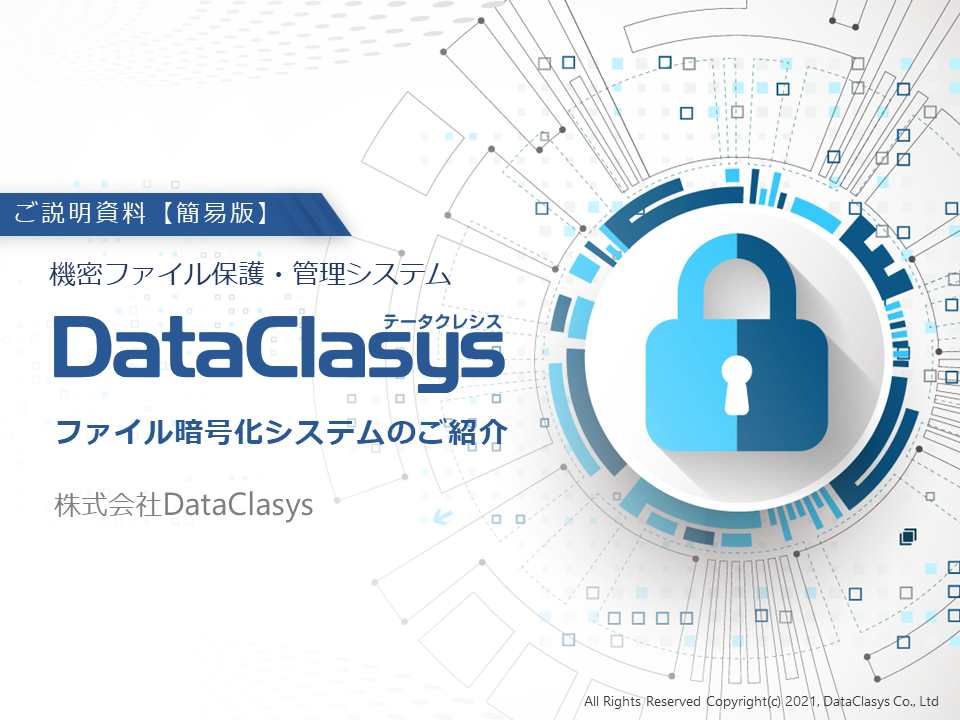
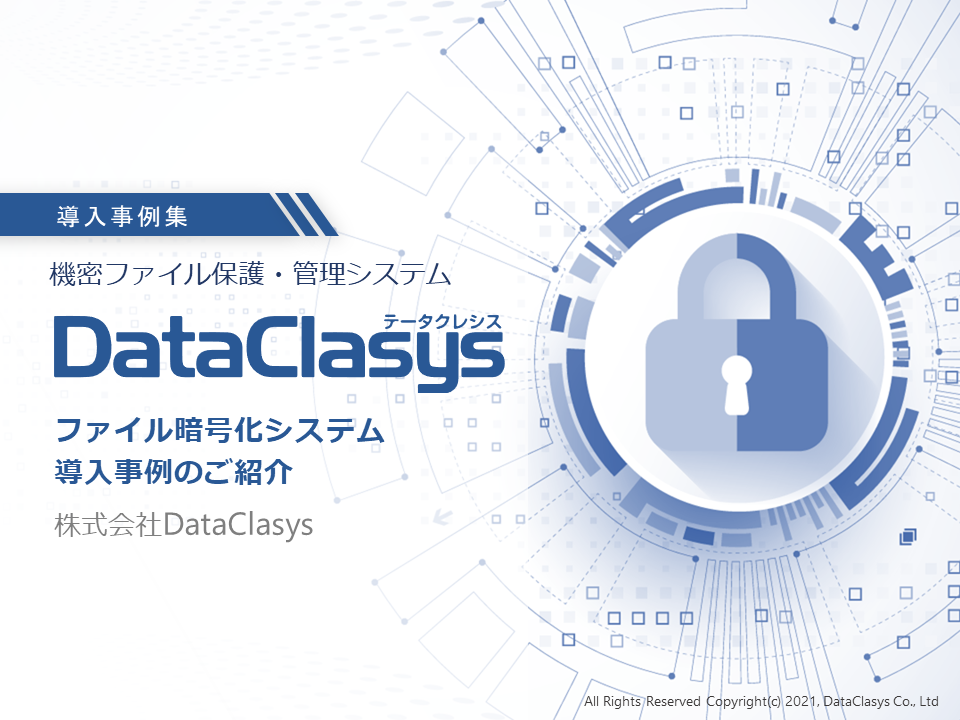
参考
[資料2]重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準(案)| 内閣府 2024年11月26日
[資料3]重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準(案)| 内閣府 2024年11月26日
最終とりまとめ | 経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議 2024年1月19日
経済安全保障分野にセキュリティ・クリアランス制度を導入し、厳罰を伴う秘密保護法制を拡大することに反対する意見書 | 日本弁護士連合会 2024年1月18日
![ファイル暗号化DataClasys [データクレシス]](/wp-content/uploads/DataClasys_logo.png)





